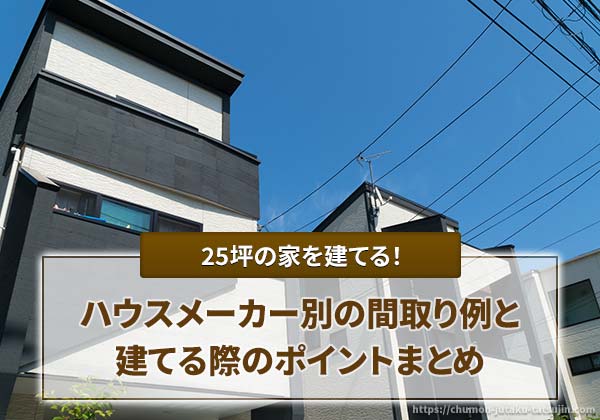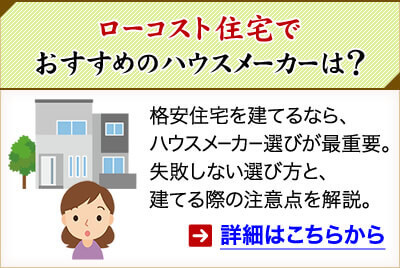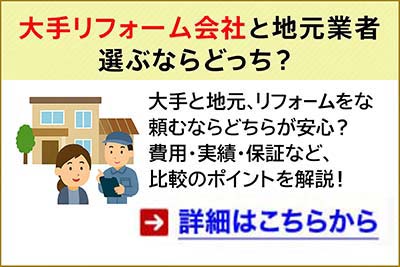「太陽光の売電って、今からでも得なの?」「制度が変わるって聞いたけど、結局どうなるの?」
近年、太陽光発電の導入を検討する中で、売電価格の低下や制度の変更に不安を感じている方が増えています。
特に2025年以降はFIT制度の終了・FIP制度の本格導入が見込まれ、売電単価も段階的に下がる傾向にあります。
つまり、これまでのように「売って儲ける」仕組みだけに頼ると期待した効果が得られない可能性も。
この記事では、売電価格の最新動向・制度変更の要点・損しない太陽光活用の考え方をわかりやすく解説します。
太陽光発電の売電制度は今後どうなる?
2025年以降の売電価格の見通し
経済産業省の調査によれば、住宅用(10kW未満)の太陽光発電における2025年度の売電単価は、1kWhあたり16円程度に下がる見通しです。
過去には40円台だった売電価格も、毎年1円ずつ下落しており、高単価で売電できる時代はすでに終わったといえるでしょう。
また、売電契約の期間も原則10年とされており、11年目以降は買取価格がさらに低下します。
固定価格買取制度(FIT)の終了とFIP制度への移行
これまでの売電は、FIT(固定価格買取制度)によって、決められた価格での長期売電が可能でした。
しかし現在は、FITに代わるFIP(フィード・イン・プレミアム)制度の導入が進んでいます。
FIP制度では、市場価格+プレミアム価格という仕組みで売電額が決まるため、収益が不安定になる可能性があります。
つまり今後は、「売って得する」から「自宅で使って得する」という視点への転換が求められています。
売電収入が下がるとどうなる?生活への影響とは
「思ったより儲からない」家庭が増加中
売電価格の低下により、「太陽光で儲けられる」という期待が裏切られたと感じる家庭も増えています。
特に、2019年以降の卒FIT世帯(売電10年満了)では、1kWh=8~10円程度での再契約となり、以前のような収入は見込めません。
導入費用の回収に10年以上かかるケースもあり、「結局、元が取れなかった」と感じる人も一定数存在します。
売電依存から「自家消費」重視の流れに変化
こうした状況を受け、最近では太陽光で発電した電気を“売る”のではなく“使う”方向にシフトしています。
自家消費を重視することで、電気料金の削減効果を最大化し、売電よりも安定的に節約できるという発想です。
特に日中に在宅している家庭や、エコキュート・IHなどの電気設備を多用する家庭にとっては、非常に効果的な活用方法といえます。
日中不在が多い家庭はどうする?損を防ぐ電気の使い方
蓄電池の活用で自家消費率をアップ
「太陽光で発電しても、昼間は不在で電気を使わない…」という家庭では、蓄電池の導入が有効です。
蓄電池があれば、日中発電した電気を夜に使うことができ、自家消費率を大きく高められます。
夜間の電気代も節約できるほか、停電時の非常用電源としても安心です。
HEMSやスマート家電で電力を効率的に活用
近年は、HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)の普及により、電力の見える化が進んでいます。
これにより、「いつ・どの家電がどれだけ電気を使っているか」を把握し、効率的な電力活用が可能になります。
また、スマート家電やタイマー機能付き家電を活用すれば、在宅中でなくても昼間に電気を使う仕組みがつくれます。
今後の制度変更にどう備える?後悔しないためのポイント
ZEH住宅やFIP制度への対応をチェック
これから注文住宅を建てる場合は、ZEH(ゼロエネルギー住宅)仕様の対応を検討するのがおすすめです。
ZEH仕様なら、断熱性や高効率設備+太陽光発電を組み合わせることで、エネルギー収支ゼロの家が目指せます。
また、FIP制度対応の販売会社を選ぶことで、長期的な売電戦略にも柔軟に対応できます。
契約内容を見直しておくべきタイミングとは
すでに太陽光を設置済みの方は、契約期間・売電単価・更新時期を改めて確認しておきましょう。
特に10年の固定期間終了前後は、再契約先や自家消費プランの見直しなど、適切なタイミングでの対応が必要です。
契約更新を機に蓄電池の導入や、全量自家消費型への移行を検討する家庭も増えています。
まとめ|売電だけに頼らない“損しない設計”を
今後の太陽光発電は、「売る」より「使う」時代です。
- 売電価格は年々下落し、収益性は限定的に
- FIP制度や市場連動価格への対応が重要に
- 自家消費+蓄電池の組み合わせで安定した節約効果
- 生活スタイルや契約内容の見直しもカギ
自分たちの暮らしに合った設備選び・制度活用をすることで、将来の後悔を防げます。
まずは、太陽光や蓄電池に強い住宅会社に相談し、発電シミュレーションやコスト比較から始めてみましょう。